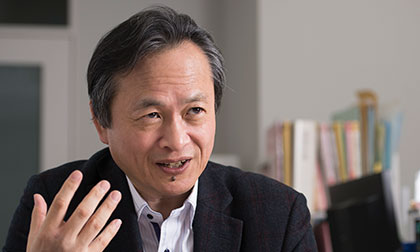
慶應義塾大学理工学部 管理工学科教授
博士(工学)
山口 高平取材・文/南山武志 撮影/大平晋也
昨年3月、英国グーグル・ディープマインド社が開発した囲碁の人工知能(AI)「アルファ碁」が、世界トップレベルのプロ棋士、イ・セドル9段に勝利し、世界を驚かせたのは記憶に新しい。この〝世紀のショー〞は、山口高平が「アルファ碁シンドローム」と称する両極端の〝誤解〞を、社会に醸成する契機ともなった。「ここまできたAIなら、例えば業務プロセスの改善などお茶の子さいさいでこなしてくれるはず」という単純な期待を膨らませた半面、「人類は、ついにコンピュータに人知を超える不気味な能力を与えてしまった」といったネガティブ発想を人々に刷り込んだのである。「こんな状態では、AIはまたブームで終わる」。進歩の妨げともなるこうした無理解の克服に向け、啓蒙活動にも取り組む男が見据える未来は、人とAIとの真の〝協働〞〝知能共進化〞だ。そこに展開するのは、どんな世界なのだろうか。〝答え〞が出ても原理が〝?〞では納得しない
山口は1957年1月、大阪市・京橋の生まれである。父親は印刷会社の場長で、時折息子に「同じ赤でもいろんな赤色があるんだ」といった話を聞かせてくれたという。幼い頃から、そんな技術屋魂に触れて育った少年が〝数字〞に覚醒したのは、小学1年から始めたそろばんがきっかけだった。
1957年1月3日、大阪・京橋で誕生。
右端が山口氏。
金属印刷の熟練技術者だった父と弟とそろばん塾には、2歳年下の弟と毎日夕方、揃って通っていました。普通は中学生の取る1級に、小5で受かったんですよ、私。5ケタくらいの足し算なら、頭の中で玉を弾いて、速攻で答えが出る。例えば、母親とスーパーに買い物に行くでしょう。当時はバーコードなんてないから、おばちゃんが1品ずつレジを打つんだけど、時々間違うわけです。それを指摘すると、「何言ってんの、ボク?」って。でも、やり直すと常に私が正解でした(笑)。
そんなふうにそろばんに導かれて、気づくと数字に強い興味を抱くようになっていました。算数の参考書を買って、いろんな計算のテクニックを勉強したり。とにかくあれこれ考えて答えを見つけていくのが好きで、逆に社会などの暗記科目は嫌いでしたね。
理科は、中学になって、多少考えて解くプロセスも増えてきたのですけど、〝なぜか?〞という原理の部分は「高校に行ってから習うこと」という感じでしょう。最後まで説明しきれていないのが、気持ち悪くて仕方ない。で、書店で高校の物理の参考書を買い込んで、一心不乱に読みました。やっぱり店のおばちゃんに「高校生違うのに、こんなん買ってどうすんの?」と、ずいぶん訝しがられましたけど(笑)。子供の頃からそんなことをやっていたのが、理工系に進む素養を培ったのは事実だと思います。
高校に入り、理数系の実力をさらに高めた山口は、「受験の数学はたぶん満点」の成績で、大阪大学工学部通信工学科に進む。「高校時代に雑誌で目にした、コンピュータに関連することをやりたかった」のが動機だった。そして大学3年の時に、〝運命の出合い〞が。やはりある雑誌の「人工知能」特集で、初めてその魅力を知ることになったのだ。ただしその当時、AI研究は決して花形分野ではなかった。
AIのどこに魅力を感じたか、ですか?コンピュータといえば、専ら早く計算したり大量のデータを蓄積したりという使われ方をしていたわけですけど、それが〝人間のように考える〞という定義自体に、すごく惹かれたんですよ。そこで研究室は、「定理証明人工知能」というAIグループがあった手塚慶一先生のところを選びました。簡単にいうと、コンピュータで数学の定理を証明しようという研究です。
ただし、グループといっても学生4人の所帯でした。手塚研究室のメインは、「計算機間通信」、今のインターネットで、AIはまあ〝異端〞といっていい存在でしたね。学問自体、正直眉唾もの的な扱いもされていて、実際卒論の発表会でも、「それをやって、社会にどう貢献していくのか?」と問われて、一言も答えられなかった。当時は、本当に興味本位で、面白いという理由だけで研究していたのです。
実は、博士課程を終えたら電機メーカーに就職するつもりだったんですよ。ドクターの3年の秋頃には、「企業に入って、第5世代コンピュータの開発プロジェクトをやろう」と、かなり青写真も明確になっていました。
ところがそんな時、阪大産業科学研究所の溝口理一郎先生が、自らの研究室にAIグループを立ち上げるので助手を探している、という話が舞い込んできたんですね。で、面接に行って「一緒にやろう」という話になった。かなり迷いましたけど、やっぱり大学にいたほうが、研究の自由度は高いわけです。就職が内定していたメーカーには怒られましたけど、AIの世界を極める道を選択しました。
属人的な現場のノウハウをAIで〝一般化〞
「研究は自由」とはいえ、基本的に興味や面白さを主たるモチベーションに研究していたそれまでと、同じスタンスは許されない。「社会に役立つ成果を」という課題が設定された研究のターゲットは、当時出始めた「エキスパートシステム(ES)」である。「定理証明で培った基礎を生かして、新しいシステムを考えよう」というのが溝口先生からのオーダーだった。
本取材は、2017年3月21日、慶應義塾大学・矢上キャンパス(横浜市港北区日吉)で行われた
ESというのは、〝エキスパート〞すなわち専門家が有している知識をコンピュータに記憶させて、それをもとに様々な問題解決などを自動的に行っていく、というコンピュータシステムです。AIの歴史はほぼ60年になりますけど、社会に貢献した最初のシステムがこれです。
余談ながら、私がメーカーに行ってやろうと思っていた第5世代コンピュータは、結局ほとんど日の目を見ることなく終わってしまったんですよ。世界一速い推論マシンをつくるというのが目標で、実際に製品は完成したのです。ところがそれを使いこなす意味は、今でいうビッグデータがあってこそ。当時は、インターネットは未発達だし、肝心のデータがありませんでした。要するに使い道がなかった。加えて1990年代初めからのコンピュータのダウンサイジングの流れの中で、ちょっとした集会所くらいの部屋が必要だったそれは、行き場を失ってしまったのです。〝社会の役に立つ〞という意味では、〝いいもの〞をつくるだけでは不十分で、時々のニーズなど多様な環境にマッチさせる必要があるということを、その時学んだ気がしています。
ESに話を戻すと、私は助手になって以降、10社くらいの企業と組んで、いろんなプロジェクトに取り組みました。例えば鉄鋼プラントの故障診断。製鉄所では、1500°Cくらいの温度で溶けている鉄を冷却水の中のパイプに潜らせて徐々に冷却していくのですが、冷やし方にムラがあったりパイプに穴が空いていたりすると、そこから高温の溶鋼が噴き出すブレイクアウトの危険性があります。そうならないために、常時センサーを見つめるその道の専門家がいて、「こういうパターンになったら、これくらい流速を落とす」といった、独自のルールを基にした制御を行っているのです。そういう人にインタビューして、ノウハウを整理したうえでプログラム化していくというのが、基本的なやり方です。
メーカーの現場の人たちは、特定の製品や事例にものすごく特化した知識を持っているんですね。それをESで〝一般化〞して、ほかの製品や部署でも活用できるようにすると、結局、その組織の競争力が向上していく。そういうのを目の当たりにすることができたのは、非常に勉強になりました。
研究所では、証券会社と組んで株価チャートの〝読み〞にも挑戦した。プロのテクニックを盛り込んだESは、メディアなどでも注目されたが、もともと理工系企業のバックアップのためにつくられた施設だけに、「株は研究テーマとしていかがなものか」といった声も上がる。人文科学系のテーマにも興味を覚え始めていた山口は89年、「より自由な研究環境」を求めて、AIの教員を募集していた静岡大学工学部へ助教授として赴任する。
静岡大には2004年までいましたが、そこで一番時間をかけてやったのが、「法律人工知能」です。具体的には、いわゆる「国際統一売買法」という契約法に関連するESの構築に向けた基礎研究で、明治学院大(当時)の吉野一教授をはじめとする法学部の先生とコンピュータ、AIの専門家合わせて30名くらいが参加しました。
例えば数量や値段を明確にした〝申し込み〞と、単なるオファー=〝申し入れ〞は法的に違うわけですね。そうした用語の意味を明確に定義して、コンピュータに理解させていく。実際にトラブルになった時に、誤りなく迅速に対処できるシステムの実現を目指すプロジェクトは、こうした分野へのAIの本格的な利用に大いに期待を抱かせるものでしたよ。
2000年ちょうどくらいから流行り始めたのが、「データマイニング」という言葉です。「データの山から価値のある情報を発掘する」という意味ですが、静岡大時代の後半には、その分野の研究にも着手していました
40年間培った”記号処理”の蓄積を知能ロボットで表現
04年、山口は慶應義塾大学理工学部管理工学科に教授として迎えられる。新天地でも、引き続き「コンピュータに言葉の意味を理解させる」「大量データから規則性を見出す」研究を2本柱に、さらには属人化、あるいはマニュアル化された知識をすべて体系化して継承する「ナレッジマネジメント」などに勤しむなか、数年前から手がけ始めたのが〝知能ロボット〞である。
今、AIの世界はディープラーニングが花盛りですが、40年間、私がどっぷり漬かってきたのは、テキストから導き出した記号、知識というものを構造化して、それをコンピュータが扱えるようにするという〝記号処理〞なんですよ。言ってみれば、元からある〝クラシカルなAI〞です。それを組織に蓄えられている個人の暗黙知を組織で共有できるようにするナレッジマネジメントに活用することによって、企業のコンピタンス、競争力を高める、というかたちで社会貢献に取り組んできたわけです。
知能ロボットをやり始めたのは、技術振興機構の「CREST」という研究資金に応募したいという話が持ち上がった時に、記号処理だけではちょっと領域が狭いので、音声や画像など、近い分野の先生たちと共同で提案しようということになったのがきっかけです。ざっくりいうと、コンピュータではなくロボットをインターフェースにして、記号処理、音声対話、画像センシング、そして手足の動作という4分野の知能を組み合わせ、1ランク上のAI、〝統合知能〞を開発するというのが、プロジェクトの目標なんですよ。
研究室の一室には、真ん中にテーブルが設えられ、おなじみの「Pepper」をはじめとするロボットが数体。脇のテーブルには、飲み物を注ぐアーム型ロボットが鎮座する。そう、ここはPepperが接客する「AI喫茶店」なのだ。
ご存知のように、Pepper君は「対話型ロボット」です。でも、実際に話したことのある方ならわかるように、ほぼ一方的にしゃべるだけ。人間の言葉を理解することは、まだほとんどできないんですよ。我々が目指したのは、そういう言葉のやり取りも含めて、お客にとっての便利さ、快適さを実感できる接客の実現です。例えば、部屋に入っていきなりロボットが近づいてきたら、たいていの人はぎょっとするはず。そうではなく、まず「いらっしゃいませ」と声がけをするといった細かな気遣いまで、実際に喫茶店のマスターの教えも請いながら、サービス改善を図っていきました。
ただし、そうしたノウハウを教え込むのに、従来のように直接プログラムをコーディングしていくやり方では、専門家しか扱えません。そこで、ユーザーが「ここはこうして」「これはダメだよ」と言葉で指示すれば、その内容がプログラムコードに自動変換される「PRINTEPS」というツールを開発しました。題して「みんなのAI」。まだ百発百中というわけにはいきませんが、言ったことの8割方は実行できるレベルになっています。
言うことを聞いてもらうための大きな鍵は、先述した言葉の理解力です。これはもう、言葉の定義を教え、それぞれの関係性を理解させ、という手作業の世界としかいいようがない。「そんなことはディープラーニングを使えば一発ではないか」と思うかもしれませんが、さにあらず。言葉の意味理解に関しては、ディープラーニングはほとんど無力なんですよ。
「PRINTEPS」の開発は、もちろんあらゆる業務の改善、合理化を展望したものですが、実用化しようと思ったら、例えばお客の表情を見て対応を変えられるようなメタレベルのAIが必要だという感触も得ました。そうした気づきも、運よく他分野と共同のプロジェクトに参加した賜物で、もし記号処理だけやっていたら、〝問題解決〞の世界から踏み出してはいなかったでしょうね。
〝シンドローム〞を超え 人とコンピュータとの 最良の関係を模索する
〝第3次ブーム〞に沸くAIだが、手放しで喜べない現実もある。「近い将来、少なくない職業がコンピュータに取って代わられる」といった認識は、社会の隅々まで浸透し、元人工知能学会会長の肩書を持つ山口の許には、企業や各種職能団体、最近では小学校からも「人の未来はどうなるのか、話してほしい」という依頼が届くようになった。冒頭に述べた〝シンドローム〞は、想像以上に深刻だ。
アルファ碁はなぜプロ棋士に勝てたのか? 答えは、計算力とデータ力で圧倒したから。ディープマインド社がやったのは、グーグル本社からパソコンを2万台借りてきて、ソフトウエア同士をひたすら対戦させることでした。彼らは、石の並んだ盤面を白黒の画像として認識するわけですが、その対戦の棋譜、「この局面でここに打ったら、最終的に勝利した」というデータをどんどん積み上げていくのです。
そうやって300万の棋譜のビッグデータ、人間なら何百年もかかるものを揃えて〝一般化〞し、何十という新たな定石も引っ提げて対戦に臨んだわけです。このように、囲碁の〝先手を読む〞というゲームの本質部分を、パターン認識に置き換えたところが素晴らしかった。ですから、彼らがやっているのは探索というより予測なのです。 あの対局以降、電機メーカーには「人の頭脳を超えたAIを使って、当社の業務を変えるシステムを構築してほしい」という依頼が引きも切らずの状況だと聞きます。勘違いしてはいけません。実際の業務が、今お話ししたパターン認識可能な世界なのかどうか、ちょっと考えればわかるはずです。
他方、あの出来事を、AIが人を超越するシンギュラリティの到来と捉えた人も少なくなかったようです。確かに計算力、データ力では、コンピュータはすでに「人知を超えた」と言っていい。でもアルファ碁だって、何か独自のロジックを組み立てて勝利したわけではないのです。言葉の理解力、抽象的思考という部分では、まだまったく人間に近づけないのが現実です。
ですから「AIが特定の職業を奪う」というのも、あまりに雑駁すぎる議論だと言わざるをえません。先日、公認会計士の団体に呼ばれて話をしたんですよ。正直、財務諸表を読むような業務はコンピュータに置き換わる可能性が高い。ただ聞いてみると、監査にしろ税務にしろ、紙に書かれていない暗黙知的なノウハウが山ほどある。AIがそこを肩代わりするのは困難です。計算はAIに任せてそこのスキルを磨けば、よりレベルの高い仕事ができるはず。どんな職業にも、人でなければできないプロセスがあると思うのです。逆に、AIに奪われない職業の一つに挙げられるセラピストだって、とおり一遍の仕事しかできなければ、置き換えられてしまうかもしれませんよ。
GAFMA(グーグル、アップル、フェイスブック、マイクロソフト、アマゾン)が主導する〝AI第3次ブーム〞の開発競争において、日本が後塵を拝した事実は否めない。だが山口は、「まだ十分勝機はある」と話す。
ディープラーニングというのは、あくまでも〝量〞の世界なんですね。そこでは、もう絶対に追いつけない。でもAIには、これからより〝質〞の部分が求められてくるはず。記号処理でしかできないところです。今後、そうした記号処理とディープラーニング系のAIとの統合というテーマが俎上に上ってくるのではないかというのが、私の読みです。そこにはGAFMAも、まだあまり手をつけてはいません。競争の余地はあると思いますよ。
個人的には、〝人とAIとの協働〞を実現するため、引き続き今の研究を前に進めるのが課題です。言葉で何か頼めば、即座にサポートしてくれる。そんなAIがみんなの傍らに普通にいるような世界を実現するのが、目下の夢です。そんな〝協働〞が進めば、両者の対話も増えるはず。人がAIに教え込むだけではなくて、逆に教わるような〝知能共進化〞のメリットも生まれてくると期待しています。
私は長年、記号処理というディシプリンをひたすら深堀りしてきましたが、知能ロボットのプロジェクトに携わったことで、多様な研究分野を横串にして一つのアプリをつくる〝トランスディシプリン〞の有用性に気づいたのです。ほかの分野とつなぐというのは、想像以上に苦労が多い反面、そこから生まれる効果も非常に大きいんですよ。若い研究者のみなさんも、そうした視点も頭の片隅に、社会に貢献していく道筋を探っていってもらいたいですね。それが私からのメッセージです。
プロフィール
慶應義塾大学理工学部 管理工学科教授
博士(工学)
山口 高平主な著書・共著など
山口氏は、著書・共著を多数出版している。
『データマイニングの基礎』(オーム社/共著)が、2007年の大川出版賞を受賞。
『法律人工知能 法的知識の解明と 法的推論の実現』(創成社/共著)。
『Practical Aspects of Knowledge Management』(Springer/編著)。
1957年1月3日 大阪市都島区生まれ 1979年3月 大阪大学工学部 通信工学科卒業 1984年3月 大阪大学大学院工学研究科 通信工学専攻 後期博士課程修了 1984年4月 大阪大学産業科学研究所 電子機器部門助手 1989年4月 静岡大学工学部 情報知識工学科助教授 1996年3月 南カリフォルニア大学 情報科学研究所客員研究員 1997年4月 静岡大学情報学部 情報科学科教授 2004年4月 慶應義塾大学理工学部 管理工学科教授 2012年6月 一般社団法人 人工知能学会会長(~14年)
職種一覧